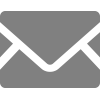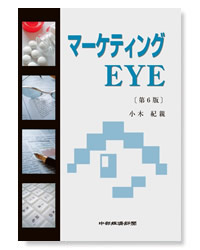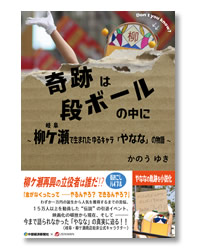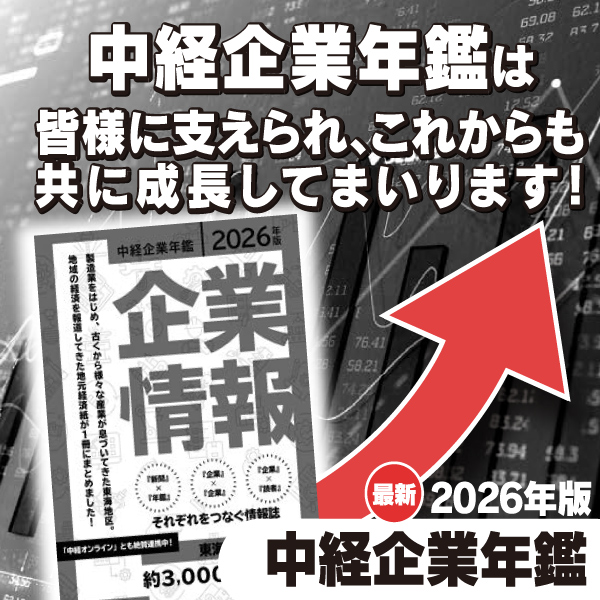環境特集
揺らぐ国際枠組みアメリカ離脱と「パリ協定」の今
世界共通の長期目標
2015年に採択された「パリ協定」は、気候変動対策における国際社会の歴史的合意とされてきた。産業革命以降の地球の平均気温上昇を2℃未満、可能であれば1・5℃に抑えるという野心的な目標を掲げ、先進国と途上国が共に温室効果ガス削減に取り組む姿勢を示した点で画期的だった。
だがその枠組みに、再び大きな揺らぎが生じている。2026年に予定される米国のパリ協定再離脱の動きが報じられ、国際協調に対する不安が高まっているのである。トランプ前政権時代の2017年、米国は一度パリ協定からの離脱を宣言し、2020年に正式に脱退。その後、バイデン政権が復帰を果たしたが、政権交代により再び国際枠組みからの撤退が現実味を帯びている。
米国は世界第2位の温室効果ガス排出国であり、その動向は国際交渉全体に決定的な影響を与える。仮に離脱が実現すれば、他国の削減努力の正当性や公平性に疑問が生じ、合意形成が難航する恐れがある。特に、排出削減に積極的でない国々にとっては「米国もやっていない」という言い訳となり、全体の行動水準を引き下げかねない。
そもそもパリ協定の採択に至るまでには、長年にわたる温暖化交渉の試行錯誤があった。1997年に採択された「京都議定書」は、先進国に法的拘束力のある削減義務を課す初の枠組みだったが、米国や中国など主要排出国が枠外にあり、実効性に限界があった。その反省を踏まえ、パリ協定はすべての国が参加する「全員参加型」のアプローチを採用。各国が自主的に削減目標(NDC=国別貢献)を設定し、5年ごとに見直しを行う仕組みを導入した。
この柔軟性により、パリ協定は195カ国以上の幅広い参加を得ることに成功したが、同時に「実効性」と「拘束力の弱さ」のバランスが課題ともなっている。現在、各国が提出しているNDCの合計では、1・5℃目標の達成には到底及ばず、現状のままでは今世紀末の気温上昇は2・5~2・9℃に達するとの試算もある。
不透明な国際炭素市場
国際的な炭素市場の設計も、いまだ曲折を重ねている。 パリ協定第6条は国境を越えたクレジット取引によって削減コストを下げることを狙うが、二重計上を防ぐ会計基準や人権保護条項の最終合意が遅れ、実現には至っていない。メカニズムが不透明なままでは排出削減量を正確に算定できず、市場全体の信頼を損ないかねない。さらに米国が離脱すれば、最大級の買い手を失う形となり、排出権市場のダイナミズムに冷や水を浴びせる恐れがある。
もっともパリ協定は単なる外交合意にとどまらない。企業や自治体、投資家など非国家主体の動きも加速しており、炭素排出に対する価格付けや脱炭素経営が、経済の新たな競争軸となりつつある。米国国内においても、州政府や大企業が独自にネットゼロ(実質排出ゼロ)目標を掲げる動きは続いており、連邦政府の方針とは異なる潮流も存在する。
それでも国際枠組みにおける最大のプレーヤーの不在は、全体の士気や信頼形成に少なからぬ影響を及ぼす。2025年には、各国のNDC再提出が控えており、その成否はパリ協定の実効性に直結する重要な節目となる。今後の米国の動向と、それに呼応する形での他国の対応が、気候外交の帰趨を大きく左右するだろう。
採択から10年が迫るパリ協定は、今まさに岐路にある。約束を履行し、信頼と協調を再構築できるか。問われているのは、各国の政治的意思と、未来への責任である。