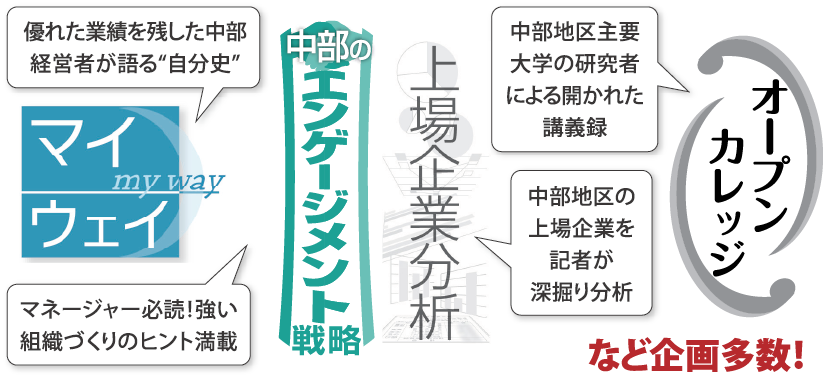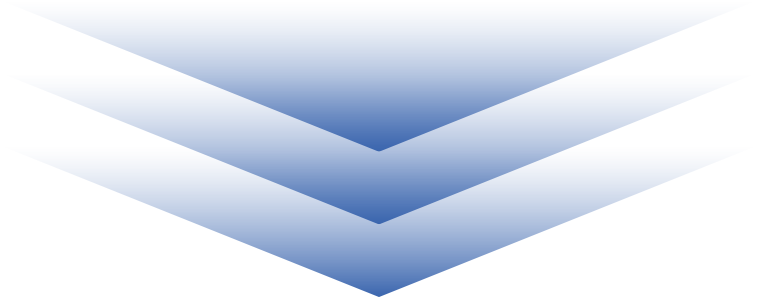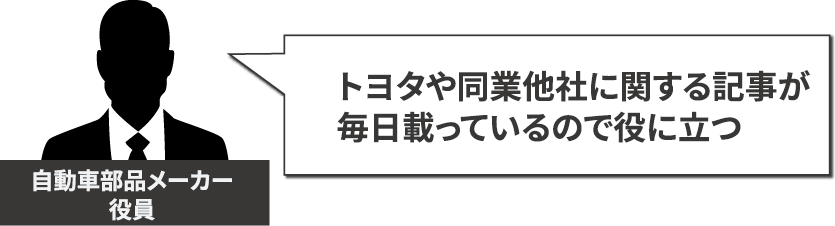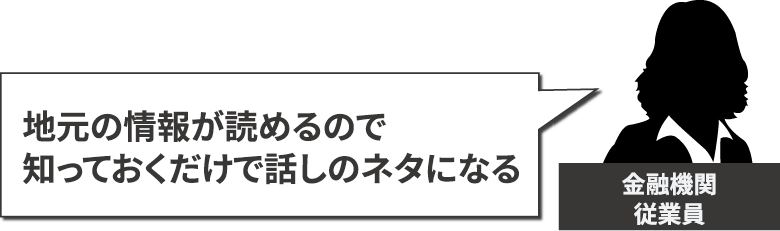「大学改革の担い手として」
東海国立大学機構機構長名古屋大学総長 松尾 清一 氏

新年あけましておめでとうございます。昨年と一昨年は新型コロナウイルス感染症拡大によって、私たちの生活は大きな影響を受けました。「アフターコロナ」「ウィズコロナ」「ニューノーマル」などの言葉が生まれ、これまでの生活が一変しました。2022年も感染対策をしながらいかに日常生活を行っていくかが、大きなポイントになることでしょう。
コロナ禍は突然襲ってきたものですが、それ以前から現代社会は激動の時代にあると言われています。環境問題、地域・民族間の紛争、食糧問題など、国際的に解決しなければならない課題が山積し、さまざまな取り組みが始まっています。その一方で、科学技術の発展に伴いイノベーションが起り、新たな技術が私たちの生活や社会を変えつつあります。
こうした変化する社会において、大学は何ができるのか、どうすれば貢献できるのか。私は長年にわたりこうした課題に取り組んできました。社会のために大学が何らかの役割を果たしていくためには、変化する社会状況に対応して大学も変わっていく必要があります。そのような思いから、大学の改革に力を注いできました。
そんな私のことを周囲は「改革の担い手」として認識しているようです。もちろん私自身にも「大学を変えてきた」という自負があります。改革には終わりはなく、これからも変えるべき点は変えていかなければならないと思っています。今までのやり方に満足していた人からすれば、何十年も続けてきた方法や組織をいきなり変えることは大変迷惑な話であり、大きな抵抗があるでしょう。しかし、「社会のために貢献する」という目標を実現するためには、そのための体制づくりから始める必要があるのです。
このような考えを持っている私ですが、最初から改革を推し進めるという考えや力を持っていたわけではありません。むしろ若い時の私は自分の将来ですらしっかりと考えることはせず、周囲に流され、行き当たりばったりで人生を歩んできた若者でした。なぜ、そのような若者が改革の担い手と認識されるようになったのか。この連載で私がこれまでの歩みの中で何を考え、どのように生きてきたかを振り返ることによって、その理由を明らかにするとともに、なぜそこまで改革にこだわるのかをわかっていただく機会になればと考えています。
〈プロフィル〉
松尾 清一(まつお せいいち)1976年(昭和51)年名古屋大学医学部を卒業し、ニューヨーク州立大学研究員などを経て、84(昭和59)年中部労災病院内科医長。2002(平成14)年名古屋大学大学院医学系研究科教授、09(平成21)年副総長、15(平成27)年総長。20(令和2)年東海国立大学機構設立とともに機構長に就任。専門分野は腎臓内科学。71歳。兵庫県出身。